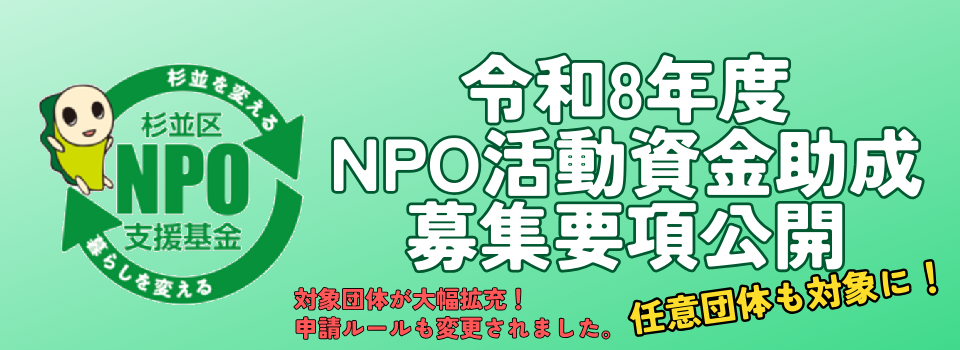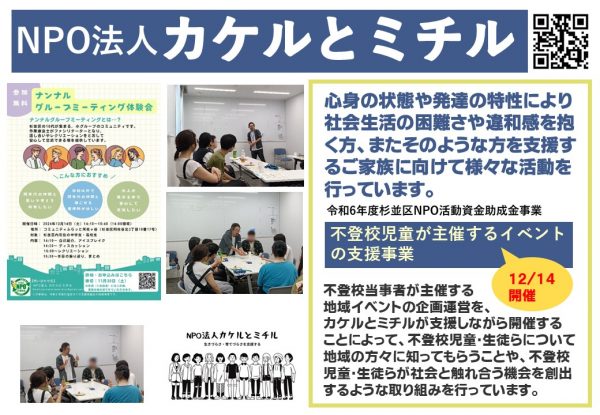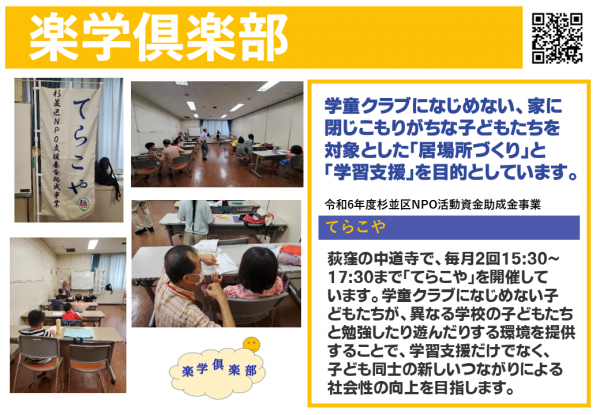杉並区内の助成金をご紹介しています。
※2024年11月時点での情報です。記載内容は変更になる可能性がありますので、最新の情報については、HPで確認するか、直接所管課にお問い合せ下さい。
<目次>
(杉並区)
(杉並区社会福祉協議会)
杉並区助成金一覧ダウンロードはこちら
■NPO活動資金助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/chiiki/kikin/1005217.html
【実施課】区民生活部地域課協働推進係
【概要】「杉並区NPO支援基金」を設置し、皆さんからの寄附と区の財源をもとに、NPO法人等が行う地域の公益的な活動に対して助成金を交付しています。助成の対象となる事業は、以下の区民を対象とした特定非営利活動に係る事業です。
・スタートアップ事業:設立5年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業
・ステップアップ事業:団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業
【助成金額】上限30万円(1事業)、総額150万円(令和6年度の場合)
【募集期間】2~3月ころ
【問合先】 杉並区 区民生活部地域課協働推進係 03-3312-2111(代表)
——————–
■次世代育成基金活用事業助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kyoiku/ikusei/1019916.html
【実施課>子ども家庭部児童青少年課少年係
【概要>次代を担う子どもたちが、自然・文化・スポーツなどさまざまな分野における体験・交流事業への参加を通して、視野を広げ、将来の夢に向かって健やかに成長できるように支援するための杉並区独自の仕組みです。
【助成金額】【助成上限額】派遣型:300万円 講座型:100万円(千円単位)
【募集期間】2月ころ
【問合先】子ども家庭部児童青少年課青少年係 03-3393-4760(直通)
——————–
■文化芸術活動助成金
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s030/news/22393.html
【実施課】区民生活部文化・交流課
【概要>区は、区内で行われる文化芸術活動事業に係る経費の一部を助成することを通して、区民や区内に拠点を持つ団体が区内で行う多様で創造的な文化・芸術活動を支援するとともに、区民の文化芸術活動への参加や地域での鑑賞機会の充実を図っています。令和6年度はこれまでの助成金に加え、若手アーティストを支援するための助成金をはじめました。
【助成金額】
・若手アーティスト文化芸術活動事業助成金:1事業当たり 上限20万円
・文化芸術活動事業助成金:1事業当たり 上限40万円
【募集期間】4~6月ころ
【問合先】杉並区 区民生活部文化・交流課文化振興担当 03-3312-2111(代表)
——————–
■まちづくり助成制度
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s092/21428.html
【実施課】都市整備部管理課庶務係
【概要】まちづくり助成制度は、住みよい都市環境づくりに貢献する区民活動に対して、活動の経費の一部を区が助成するもので、まちづくりの気運を醸成し、地域の活性化と住環境の向上を図ることを目的としています。
助成の募集は、(A)びぎなーコース、(B)すてっぷコースがあります。
【助成金額】 びぎなーコース 3万円/年 ステップコース 7万円/年
【募集期間】4~5月ころ
【問合先】都市整備部管理課庶務係 03-3312-2111(代表)
——————–
■ささえあい活動助成(長寿応援ファンド)
※令和6年度末をもって、ささえあい活動助成(長寿応援ファンド)制度は終了となりました。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/koureisha/ikigai/choju/1012491.html
——————–
■まちの絆向上事業
https://www.sugi-chiiki.com/chouren/docs/oshirase_machinokizuna_r7.pdf
【実施課】区民生活部地域課
【概要】町会・自治会及び地区町会連合会(以下「町会等」という。)が、まちの絆を強め、 町会等への加入促進やコミュニティ活動の活性化を図るための事業の実施を支援 することを目的とした助成金です。
【助成金額】
・一般型
町会・自治会 1事業に対して20万円まで 地区町会連合会 1事業に対して40万円
・地域連携支援型
町会・自治会 1事業に対して25万円まで 地区町会連合会 1事業に対して50万円
【募集期間】年4回(第1回:3月頃 第2回:4月頃 第3回:9月頃 第4回:11月頃)
【問合先】杉並区区民生活部地域課 03-3312-2111(代表)
——————–
■地域福祉活動費助成
https://www.sugisyakyo.com/vol/chiiki_josei.html
【実施課】 社会福祉協議会 地域支援課 杉並ボランティアセンター
【概要】地域福祉活動費助成金は、歳末たすけあい運動の募金をもとに、世代を超えた「地域のつながり」づくりなど、地域福祉を推進する活動(事業)に助成します。
【助成金額】助成の種類と助成上限額
・チャレンジ応援助成:1事業上限50万円
・定例活動活性化助成:1事業上限20万円
【募集期間】12月ころ
【問合先】杉並区社会福祉協議会 地域支援課杉並ボランティアセンター03-5347-3939
——————–
■子ども支援活動費助成
https://www.sugisyakyo.com/kanri/child_josei.html
【実施課】 社会福祉協議会 経営管理課管理係
【概要】~地域の想いを子どもの笑顔に~
すべての子どもたちが健やかに育つことを目的に、子どもの福祉向上に資する活動の主催団体に助成金を交付します。
【助成金額】1団体につき10万円を上限とします。(令和6年度助成総額 200万円上限)
【募集期間】11月ころ
【問合先】杉並区社会福祉協議会経営管理課管理係 03-5347-1010