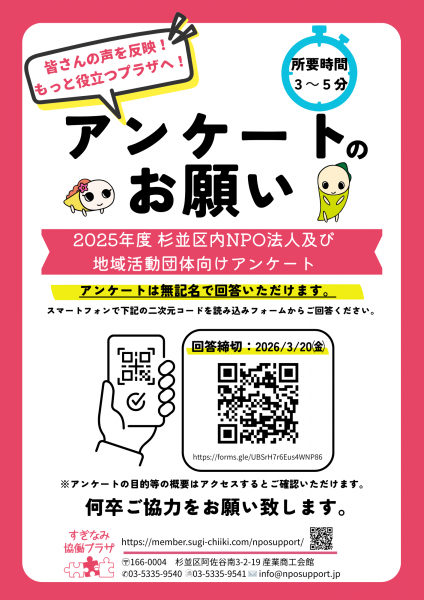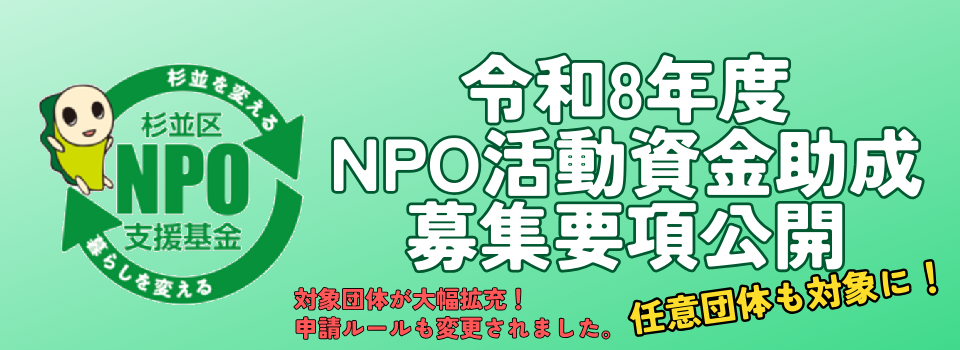【重要】杉並区NPO活動資金助成がリニューアル! 今年度から対象団体が大幅に拡充され、申請ルールも変更されました。
・対象の拡大:NPO法人に加え、任意団体や一般社団法人等も対象に!
・必須要件:申請するには、すぎなみ協働プラザに登録済みの団体であることが要件となりました。未登録の方は早めにお手続きください。
申請に先立ち、2月18日(水)に『募集説明会』が開催されます。説明会に参加しなくても申請は可能ですが、初めて申請する方は参加をご検討ください。
まずは下記詳細をご一読いただきますよう、お願いいたします。
■令和8年度杉並区NPO活動資金助成
杉並区は「杉並区NPO支援基金」を設置し、皆さんからの寄附と区の財源をもとに、NPO法人等が行う地域の公益的な活動に対して助成金(NPO活動資金助成)を交付しています。
本助成金に関しては、すぎなみ協働プラザで事前相談及び申請を受け付けます。
●対象団体:
【令和8年度の募集から、募集対象団体が下記のとおり拡大されます。】
◆7年度まで◆:NPO法人、すぎなみ地域大学修了生
↓↓↓
◆8年度から◆:NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、任意団体《町会・自治会・学校支援本部等をのぞく》
※杉並区内で活動する、すぎなみ協働プラザに登録済みの団体であることが要件です。
制度の活用を検討している団体はぜひご確認ください。
●助成金額:上限30万円(1団体あたり)※助成総額150万円(予定)
●対象事業:以下の区民を対象とした特定非営利活動に係る事業です。
・スタートアップ事業:設立5年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業
・ステップアップ事業:団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業
●申請受付期間:令和8年2月10日(火)~3月13日(金)
●募集案内・申請書類:令和8年2月2日(月)以降にすぎなみ協働プラザで配布します。また、2月1日(日)以降杉並区公式ホームページからダウンロードすることもできます。
ダウンロードはこちら
⇒https://www.city.suginami.tokyo.jp/s019/news/23825.html
このページの下記にも募集案内等へのリンクがあります。
●申請方法:事前に電話またはEメールで予約の上、すぎなみ協働プラザに申請書類を持参してください(郵送不可)。
※提出書類に不備等がありますと、再提出をお願いする場合があります。再提出も含めて受付終了日が3月13日になりますので、余裕を持ってご提出ください。
●事前相談期間:令和8年2月10日(火)~3月6日(金)
※申請書類の提出に当たっては、事前相談が必須となります。事前に電話またはEメールで予約の上、記載済みの申請書類を持ってすぎなみ協働プラザへお越しください。
●団体登録:事前に下記リンクの「来所予約はこちら」のボタンまたは電話、Eメールで予約の上、すぎなみ協働プラザへお越しください。
※団体登録には審査があり、お時間を要します。申請を検討している場合はお早めに団体登録の手続きを行ってください。(申請期限までに団体登録が完了していない場合は申請を受け付けることが出来ません。)
⇒https://member.sugi-chiiki.com/nposupport/dantaitouroku/
~~~~募集説明会を開催します~~~~
●日時:令和8年2月18日(水)18:00~19:00
●会場:杉並区役所分庁舎3階(成田東4-36-13)
●定員:20名(1団体2名まで、申込順)
●申込方法:令和8年2月13日(金)までに電話またはEメールで、すぎなみ協働プラザへお申し込みください。
電話:03-5335-9540
Eメール:sanka@nposupport.jp
Eメールの場合は「団体名」「参加者名」「連絡先」「質問事項(希望者のみ)」を明記の上、ご連絡ください。
当日に質問したい内容を、事前に受け付けます(希望者のみ)。お申し込み時にお知らせください。
なお、事前に受付する質問は、参加者全体に関わるものに限ります。個別具体的な相談は、別途すぎなみ協働プラザへお問い合わせください。
●その他:募集説明会に出席しなくても申請できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●問合せ:すぎなみ協働プラザ
Eメール:info@nposupport.jp
電話:03-5335-9540